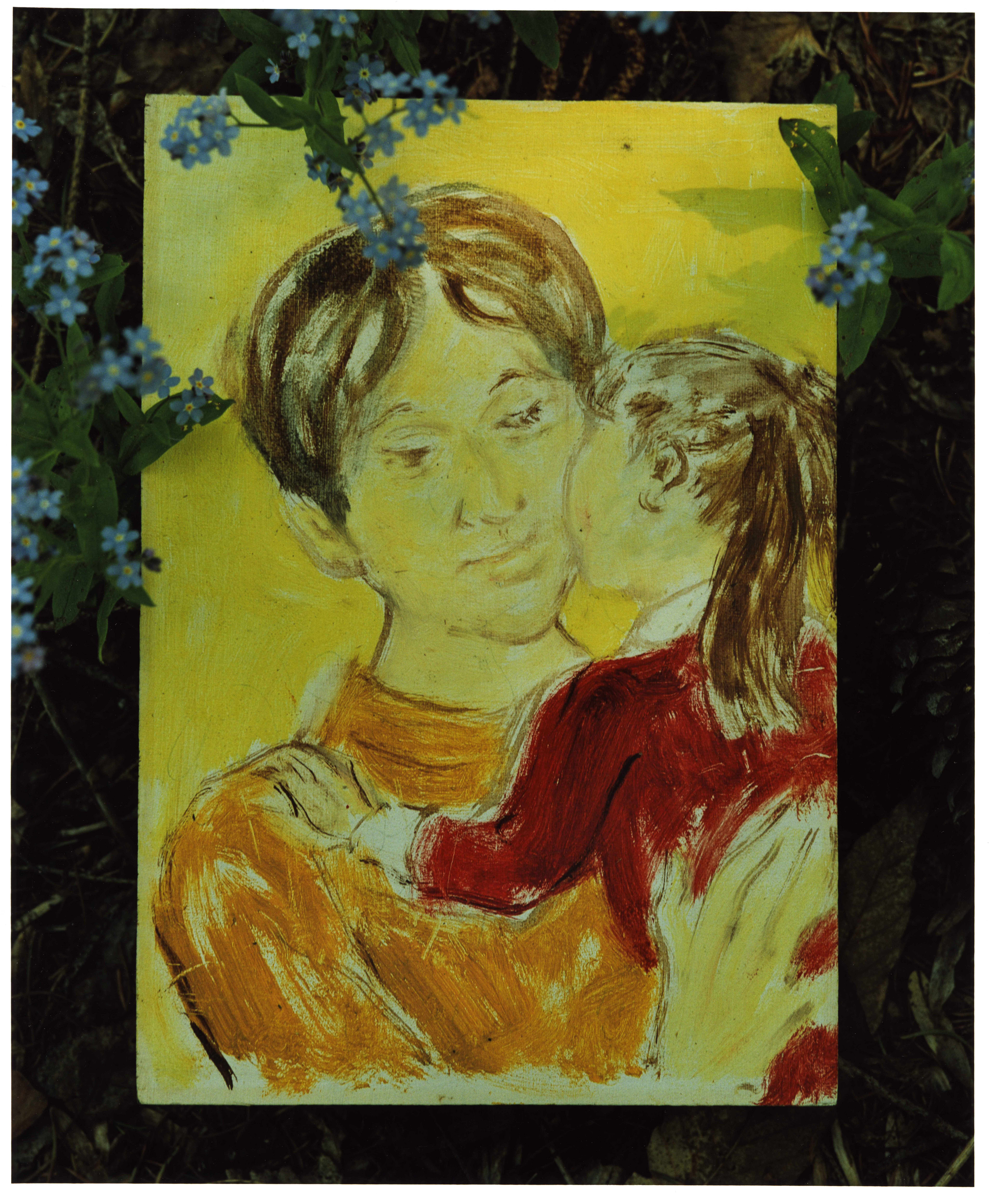弁造さんの庭で行うエスキースの撮影のはじまりは春のことだった。理由はさほどない。ただ、北国に暮らす者が新しい何かを始めるとき、その時期はやはり春だと思う。対象への思いを深め、行動の計画を練っていく作業を雪が降り積りって静けさが支配する冬が助けてくれる。
行動という意味では雪に覆われる冬に閉塞感を覚えなくもないが、思索を広げる場と捉えると全くの逆で美しいほどの自由がそこにある。野に暮らす生き物はもちろんのこと、土や木のざわめきまでをも鎮め、風景をつくっている確かな存在のすべてを抽象化していく雪景色は、終わりも始まりもなく募らせる思いを描くためのカンバスとなって人の前に立ち上がる。
あの年の冬、僕は雪原の向こうに弁造さんが描き、遺したエスキースの黄色や緑といった鮮やかな色彩を幾度となく思い起こした。冬の光は鈍く乏しかったが、想像のなかのエスキースはいつもそれ自体が発光でもするかのように、穏やかでいて強さのある光と、その光がつくるひだまりを削り取った尖った影を伴っていた。それは、弁造さんの丸太小屋のあのビニールの窓を通して届けられる光がエスキースの上で作り出す光と影の表情を思わせた。
岩手から北上して青森からフェリーで海峡を渡り、何時間も運転して弁造さんの庭に着くと、僕が暮らしている岩手よりも少しだけ若い春が迎えてくれた。桜の時期はもう終わっていて林床には萌黄色の緑が広がっていた。その瑞々しい緑のなかで一際目を引いたのは忘れな草の冷たさを宿した青だった。とても小さな花だが隙間を埋めるように群生して咲く様子は、遠目から見ると柔らかな青い布でも広げたようだった。この光景は不思議な印象を僕にもたらした。もう20年以上にも渡って繰り返し訪れてきた弁造さんの庭だったがこんな風に林床が忘れな草の青で埋まる姿は記憶になかったからだった。
僕は忘れな草の花たちを潰してしまわないように注意しながらエスキースを固定するための台を置いた。岩手から車に積んで持って来た段ボールには、たくさんのエスキースが入っていた。この中からどの一枚を選べば良いか。それはエスキースの撮影をどう始めるかということでもあった。一瞬の逡巡があったがこの感情は無視することにした。エスキースは弁造さんが弁造さんの魂と手で描いたものであって僕は一切関わってはいない。今の僕の役割は弁造さんにエスキースを返すだけなのだ。
段ボールの中から無造作に取り出したのは、母と娘を描いた小さな油絵のエスキースだった。弁造さんのエスキースは大きく分けると紙と板に描かれたものがあり、板は油彩によるものだった。5mmのベニヤ板を適当な大きさに切り、白の絵具で下地を作ってから描いていくという手法によるエスキースは、弁造さんが遺したエスキースの中心的存在だった。弁造さんが逝ってしまったとき、ベッドの上の棚には下地の白が塗られ、あとはモチーフが描かれるの待つだけの板がたくさん残されていた。絵を完成させるときはカンバスに描くと言っていた弁造さんだったが、板という少し荒々しさの残る素材に色を置くのが性に合っていたのかもしれない。
僕は台の上にエスキースをそっと置き、三脚を立てカメラをセットし終えるとファンダーを覗き、ピントの調整ノブをゆっくりと回した。写真を長くやってきたのでピントを合わせるという行為は身体が覚えている。それでも、レンズの先にある対象が徐々に像を結んでいくというマニュアルフォーカスレンズ特有の視覚の変化には、写真の謎を突きつけられたかのような奇妙な感覚を味わう。僕自身が見たかったものが本当にこれなのかとカメラに問われているような気もするし、「いまここ」という、ある意味では抽象極まりない「現実」なるものがこうして小さなファインダーに顕れることの不思議を強いリアリティを伴って覚えるからだ。
ピントが合うと、母が幼い娘を抱いて向かい合う姿がファインダーの中にはっきりと現れた。「母と娘」は弁造さんが生涯持ち続けたモチーフだった。基本的に弁造さんは女性だけを描いた。ただ、描かれる女性たちは弁造さんからいつも遠い存在だった。南国と思しき場所で木漏れ日を浴びる半裸の女性。朝の柔らかな日差しを浴びて頬杖をつく女性。こうした女性たちの佇まいは弁造さんの日々の暮らしとはかけ離れていて、僕は彼女たちにリアリティを感じたことはなかった。その一方でモデルを立てることなく弁造さんの想像からのみ描き出される女性たちだからこそ、弁造さんがその胸で思い描く弁造さんだけの女性のそのものであると思えた。しかし、繰り返し描かれる母と娘はそうではなかった。同じように想像から描き出される二人ではあったが、その表情、着ている服、髪型には僕の知らない「誰か」の存在を思わせた。この「誰か」について弁造さんが口にすることは生涯なかったが、僕との付き合いのなかで弁造さんが唯一完成させた絵が「母と娘」だったことを考えると、特別なモチーフだったことは間違いないだろう。
最初の写真を撮るために、たまたま手にした一枚のエスキースが弁造さんにとって大切なモチーフであったことに安堵した僕は、もう一度ピント調整ノブを前後させて微調整した。ファインダーは黄色味を帯びた母の表情をさらに鮮明に浮かび上がらせた。お下げ髪姿の娘は母に抱き抱えられたまま、頬に口づけしているのだが、角度的にその表情は見えない。母はほんの少し首を傾げて娘の唇に自らの頬を近づけていた。その目元には大袈裟ではない笑みが見て取れる。特別な瞬間ではない。きっと、日々のなかで繰り返される母と幼い娘の触れ合いなのだろう。弁造さんは、こうした母娘の何でもない時間を何度も描くなかで何を思ったのだろうか。
僕はファインダーから目を離し、レンズの先にあるエスキースを直接見つめると、静かにシャッターを押した。間髪入れず、中判カメラの大きなミラーが森に響くほどのけたたましい機械音を立てて、フィルムを露光させた。
母と娘のエスキースをもとの段ボールにしまい、台も取り去ると忘れな草たちが再び澄んだ青を広げた。ふと、忘れな草の英名が「foget me not」だったことを思い起こした。「わたしを忘れないで」。そこには日本名にはない「わたし」の存在が強く語られていた。
弁造さんが逝ってしまい、10年の月日が流れようとしていた。その間、僕は写真集や随筆集の制作を通じて、弁造さんという存在を常に身近なものとして捉えてきた。感覚的には弁造さんの「生きること」が自分のなかで語り続けられている状態で、対象を自分の外に置くことで変化する「忘れる、忘れない」といった感情とは違うものだった。しかし、だからといって弁造さんを他者以外の何者かと思ったことはなかった。弁造さんのことをいかに考えようとも答えを得ることはできない。この絶対の約束が僕が弁造さんのこと延々と考え続けることを可能にする源泉でもあった。
でも、それでもいつか忘れる日がやってくるかもしれないと目の前の忘れな草は問いかけていた。いつかは忘れる。いつかは忘れ去られる。僕が気になったのはこの二つの感情についてだった。人が動物たちと決定的に異なる点を一つ挙げるとしたら、それはきっと記憶に対する感受性だろう。いや執着と呼んだ方がいいかもしれない。人という生き物は記憶の継承によって自然の中で生き抜く術を身につけてきた。しかし、人が大切にしている記憶とは、そういった具体的なかたちで生存につながるものだけではない。それは言うなれば、魂や心といった見えない領域を守り続ける記憶である。それは僕たちの言葉で言うと思い出と呼ぶもので、もし、これがすべて失われたとしたら、僕たちは自己を保ち生きていくのができなくなるのだろうか。そのことを僕たちは知っているからこそ、ここまで記憶を大切にし、忘却を怖れるのだろうか。だからこそ人は野に咲く小さな青い花にさえ、「foget me not」という言葉を呟かせるのだろうか。忘れ、忘れ去られることで僕たちは何を失うのだろうか。それは、たとえば僕であれば、弁造さんのことを忘れなければ知ることができない結果なのだろうか。
自己と他者というふたつの存在があり、二者が関係を結べば、その二者を結ぶ記憶が双方に生まれる。いつの日か、この記憶が一方から解かれて消え、やがて他方からも静かに解かれてやはり消えていく。人という生き物はこの記憶の消滅を拒むことができないと知りながら、脳裏に映し出される記憶の緒を握りしめ、そこにすがりつこうとする生き物なのだろうか。
僕は弁造さんが描いた母と娘の残像を追いかけるように忘れな草が広げる澄んだ青を見つめ続けていた。